「部下がミスをした。このとき、叱るべきか、それとも何も言わずに見守るべきか?」
多くの上司が、一度はこんな悩みに直面したことがあるでしょう。
正解は一つではありません。 でも、判断の軸を持っていれば、どんな状況でも落ち着いて対応できるようになります。
この記事では、部下の成長を本気で願うあなたに向けて、「叱る」と「見守る」をどう使い分けるかを、実例も交えてわかりやすく紹介します。
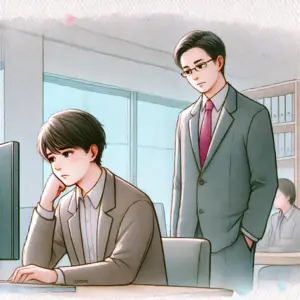
1. なぜ叱るのか?目的を意識しよう
「叱る」とは、感情をぶつけることではありません。 間違いを正し、次にどうすべきかを伝えるための大切なコミュニケーションです。
叱る理由があいまいなままだと、ただの怒りと受け取られてしまいます。
叱るのは、相手に期待しているからこそできることです。
2. 相手と状況に合わせて対応する
すべての部下に同じ接し方をしても、うまくいくとは限りません。
経験の浅い新人には丁寧な説明が必要ですが、ベテランには自主性を尊重する姿勢が大切です。
相手の性格やその日の状態をよく見て、適切な声かけを選びましょう。 たとえば、落ち込んでいるときには静かに寄り添う言葉が効果的ですし、前向きな気持ちのときには背中を押す一言が力になります。
3. 日常の信頼関係が“叱る力”を支える
ふだんあまり話をしない上司から急に叱られると、「なぜ今になって?」と不信感を持たれることもあります。
信頼関係は日常の小さな積み重ねから生まれます。 雑談や挨拶、ちょっとした声かけなど、日々の関わりがあってこそ、叱ったときにも素直に受け止めてもらえるのです。
小さな声かけが、大きな信頼を育てるきっかけになります。
4. 褒めることも忘れずに
叱るだけでなく、良いところにもしっかり目を向けましょう。
結果だけでなく、その結果を出すまでの努力や工夫にも注目することで、部下は「見てもらえている」と感じ、自信を持てるようになります。
人は、叱られて変わるよりも、信じられて変わる。
5. 感情的に叱らず、冷静に伝える
イライラしたまま叱ると、相手は防御的になり、内容が伝わらなくなってしまいます。
叱る前には、一度深呼吸をして気持ちを落ち着けましょう。 何を伝えるべきかを整理し、相手の立場を考えながら、冷静に言葉を選ぶことが大切です。
おわりに:迷ったときに役立つ“判断の軸”を持とう

「叱る」「見守る」——どちらが正しいかを悩むのではなく、「今、この人には何が必要か?」と考えることが大切です。
迷うのは、相手のことを真剣に考えている証拠。 だからこそ、自分なりの考え方の軸を持っておけば、状況に応じた最善の対応ができるようになります。
あなたの接し方ひとつで、部下の未来は大きく変わるかもしれません。 まずは今日、ひとこと声をかけてみることから始めてみませんか?
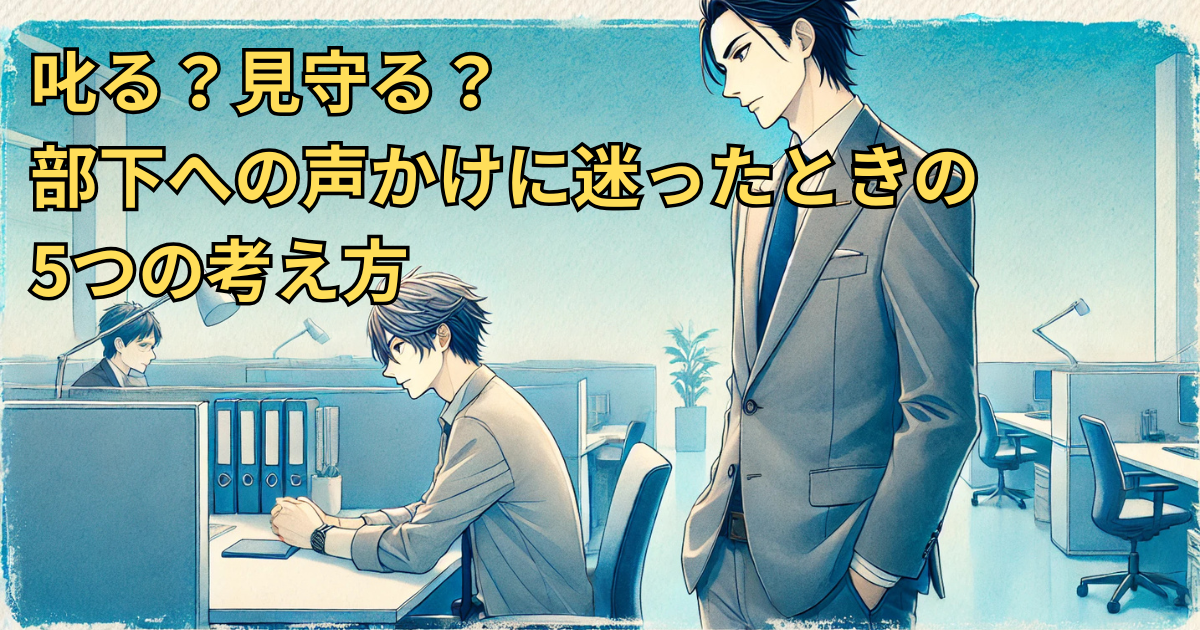
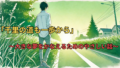

コメント